絆整理サポート代表の大山です。
テレビなどで「ゴミ屋敷の片付け」企画の番組がたまにありますよね。
「うちの親は几帳面だから大丈夫」など他人事に思っている方が多いと思います。
ですが、実は
ゴミ屋敷の住人=片付けられない人
ではないんです!
物を大量に堆積させ、いわゆるごみ屋敷を形成している住人は大きく2つに分類することができる。一つ目は「ごみを片付ける能力がない人」で、認知症や身体疾患、精神疾患など(反復性の気分障害や慢性の統合失調症残遺状態など)のためであることが多い。生活を支えていた家族の喪失や疾病の悪化による生活スキルの破綻が契機になりやすい。破綻した生活を見られたくない、知られたくないという思いから、結果としてセルフ・ネグレクト(自己放任)に至っていることも少なくなく、8050問題とも関連する。生ごみを含むあらゆる生活ごみが堆積してゆく傾向があり、ネズミや衛生害虫の繁殖、悪臭など地域の問題となりやすい。
二つ目は「堆積物をごみだとは認識していない人」である。このタイプは、特定の物へのこだわりが大きく、「愛着がある大切な物なので捨てられない」と排出を拒否し、「使えるのでもったいない」と近隣から収集してくるケースもある。片付ける動機がなく、本人は困っていないため、他者の介入を嫌い、自ら積極的にセルフ・ネグレクトになっていることも少なくない。神経発達症群(DSM-5:米国精神医学会:「精神疾患の分類と診断の手引き」による「発達障害」や「知的障害」に代わる和訳呼称)や妄想を伴う精神疾患(妄想型統合失調症や妄想性障害など)、DSM-5で新たに分類された「ためこみ症」と診断される事例などが含まれる。特定の物が堆積していく傾向があり、行政が代執行等で一時的に片付けても再燃する可能性が高い。
ごみ屋敷への対策の第一歩は、「ごみ」をひとくくりにせず、何がどのような時間経過でどのように堆積していったのかを細かく情報収集し、医療や福祉、法律などの専門家の視点も加えて多角的に対策を立てることである。
出典:「いわゆるごみ屋敷への精神保健福祉の視点からの考察」
菅原 誠
東京都立中部総合精神保健福祉センター副所長
(公財)東京都医学総合研究所客員研究員
このように、物を片付けられない背景には精神との密接な関係があります。心の病は見た目では気づきにくく、気づいた時には深刻な状況に陥ってしまっている、ということも珍しくありません。
私もこれまでゴミ屋敷の整理の経験がありますが、そのたびに「家族や社会とのコミュニケーションが途絶え、心の健康が損なわれた結果」だということを感じてきました。
大切なご家族がそのような状況に陥らないためにも、日頃からコミュニケーションを大事にしていきましょう!
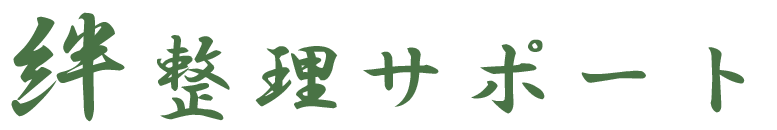
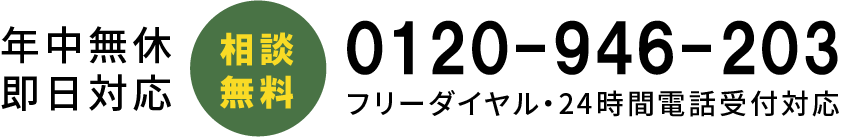

-7-640x360.png)
